「魏志倭人伝」の記述を正しく読み解くには、誤訳や写本の差異に対する深い理解が欠かせません。
この記事では、ギリシャ考古学におけるアルテミス神像の誤訳事例を手がかりに、文献解釈の難しさと落とし穴を探ります。
そして、魏志倭人伝に見られる書き間違いや記述矛盾の背景として紹興本・紹煕本の違いに注目し、文献批判的視点の重要性を考察します。
ギリシャ考古学に見る誤訳の実例とその影響
アルテミス神殿の誤訳問題
1970年代に、ギリシャで考古学を揺るがす大発見がありました1。
ギリシャの考古学者たちは、古代文献の「エレトリアの城壁から7スタディオン」という記述を頼りに、アルテミス神殿の跡を捜索していました。
彼らは当然その範囲を重点的に調査しましたが、神殿は見つかりませんでした。
そんな中ある研究者が、写本の文字が間違っているという説を発表します。
「数字の7は文字ζ(ゼータ)に置き換えられる。これは数字の60を表す文字ξ(クシー)と非常によく似ている。つまり写本家がζをξと間違えた可能性がある。」
すなわち、7スタディオンは60スタディオンの誤写ではないかと考えました。
実際に再調査を行った結果、60スタディオン離れた地点で神殿跡が発見されたのです。
ζ(ゼータ):7スタディオン(約1.25キロメートル)
ξ(クシー):60スタディオン(11キロメートル弱)
この事例から学ぶ歴史文献解釈の注意点
アルテミス神殿に関する誤訳事例は、歴史文献を解釈する際の注意点を明確に示しています。
文献は、時代や文化背景、文体の違いによって意味が大きく変わることがあり、現代語への翻訳過程での解釈ミスが、研究の方向性を誤らせる要因になります。
特に、写本が複数存在する場合、どの系統の本文を用いるかによって結論が異なることもあります。
このように、一見些細な訳語や表現の違いが、歴史像の構築に重大な影響を及ぼす点を意識する必要があります。
魏志倭人伝も「誤写されたかもしれない」
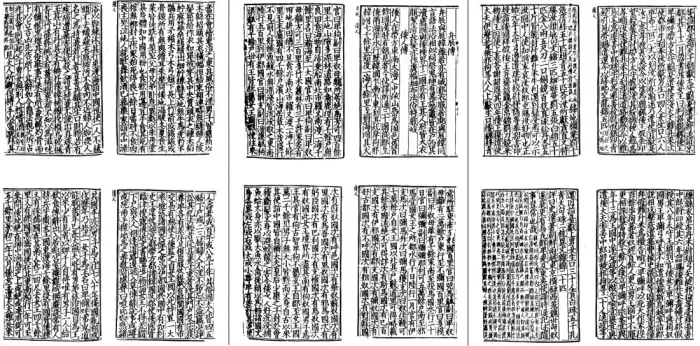
魏志倭人伝(三国志)をはじめとする中国の史料は、文字文化の無かった時代の日本が記録された貴重な文献です。
しかし、この書物の原本は現存しておらず、私たちが読めるのはすべて写本です。
しかも、これらの写本は中国・宋代以降のものであり、複数の版本(紹興本・紹煕本など)が存在します。
写本文化において最も恐ろしいのは、一文字の誤写が全体の意味を根底から変えてしまうことです。
とくに『魏志倭人伝』のような地理・制度・風俗を記述する史料では、そのリスクは極めて重大です。
その誤写は決して突飛な間違いではなく、「人の目」で書き写す作業の中で自然に生じる、見た目のよく似た漢字の取り違えによるものが大半です。
草書・行書の時代的背景
写本が作られた時代背景を考えると、書写に用いられたのは多くの場合、草書や行書といった略筆体です。
これらの書体では、字の省略や変形が日常的に行われていたため、文字同士の区別がつきにくいという構造的な問題があったのです。
線を一画ずつ丁寧に書く「楷書体」
何本かの線を続けて書く「行書体」
さらに文字をくずした「草書体」
魏志倭人伝でも、紹熙本では對海國(対海国)、紹興本では對馬國(対馬国)と違いがあります。
これは前後の文が完全一致していることから、海と馬という漢字の誤写である可能性がかなり高いと予測されます。
正確な歴史認識のために研究者ができること
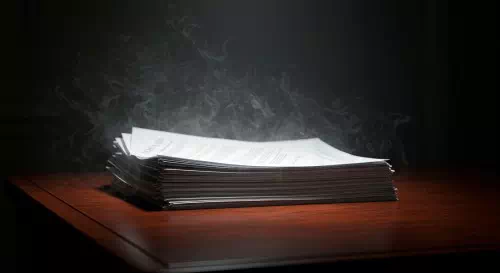
正確な歴史認識のために研究者ができることは、原典の綿密な読み直しと、異なる写本や翻訳の比較を通じた検証です。
アルテミス神殿に関する誤訳の事例でも、原語表現の再検討によって従来の誤解が正されました。
文献に依存する研究では、写本の違いや訳語のニュアンスのずれが、解釈の誤りにつながる危険があります。
研究者は常に複数の資料に当たり、文脈や表現の意味を丁寧に読み解く姿勢が求められます。
テキストクリティークという研究手法
テキストクリティークとは、複数の写本や版を比較し、どの語句や表現が原文に最も近いかを検討する研究手法です。
歴史文献における誤記や書き換え、伝承過程での変化を明らかにすることで、信頼性の高い本文を再構築することを目的としています。
紹興本・紹煕本のように異なる伝本が存在する場合、この手法は極めて有効であり、文献の中でどの表現が意図されたものであったのかを科学的に探る重要な手がかりとなります。
ギリシャ考古学の事例を踏まえた今後の視野
ギリシャ考古学におけるアルテミス神殿の再発見は、誤訳や見落としの修正によって新たな歴史像が浮かび上がることを示しました。
この事例は、魏志倭人伝のような古典文献にも応用可能であり、写本ごとの違いを丁寧に検討し、文献の背景や語句の意味を再検証する姿勢が重要です。
今後の研究では、他分野の方法論も積極的に取り入れ、文献解釈の精度を高める柔軟な視野と多角的な検討が求められます。
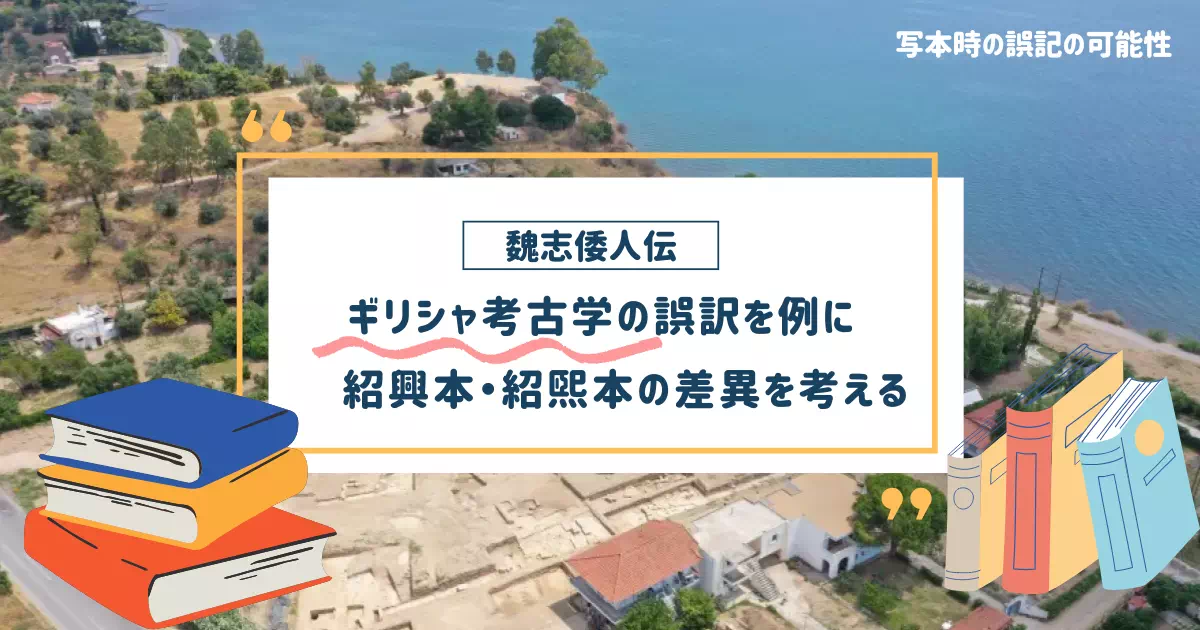
コメント