『晋書』は265~420年の中国のことを記述している史料ですが、卑弥呼に関する記述もあります。
ただし成立時期が時代的に離れているため、邪馬台国論争の史料として使えるかどうかの議論から必要になります。
目次
晋書とは
晋書は、帝紀10巻・載記30巻・列伝70巻・志20巻からなる、中国の晋国についての歴史書です。
卷97 列傳第67 四夷傳には中国周辺の国について記述されており、その中には倭に関する記述もあります。
史料データ
| 著者 | 房玄齢(総監)、他数名で編纂 |
| 成立年 | 648年 |
房玄齢は578~648年の唐の歴史家です。
唐の第2代皇帝である李世民は、房玄齢を総監として未編纂の史書を作ることを命じました。
そこで『北斉書』『梁書』『陳書』『隋書』『周書』『晋書』が一斉に編纂されています。
一斉編纂とは言っても、史料成立順と歴史の流れは一致しません。
265~420年の晋国のことを書いた『晋書』は646~648年に編纂されています。
581~618年の隋国のことを書いた『隋書』は636年から編纂開始しています。
信憑性
メリット
- 晋国に関する史料ながら、年代が近い三国時代や後漢の話も掲載している。
- 諸書から前代の記録を広く考証しており、資料収集面は高く評価されている。
デメリット
- 内容の正確性については批判的な評価が多い。
- 複数の編者がいるため前後矛盾の内容などがある。
晋書は晋国滅亡からかなり後に編纂されていることあり、それまでの史料を広く参照しているとされています。
また、晋国以前の内容も必要に応じて入れられており、多数の史料から総合的に晋国のことを記述できているとされています。
しかし、デマや誤報が多く入っていると思われ、内容の信憑性・正確性には難があるとの見方が多いようです。
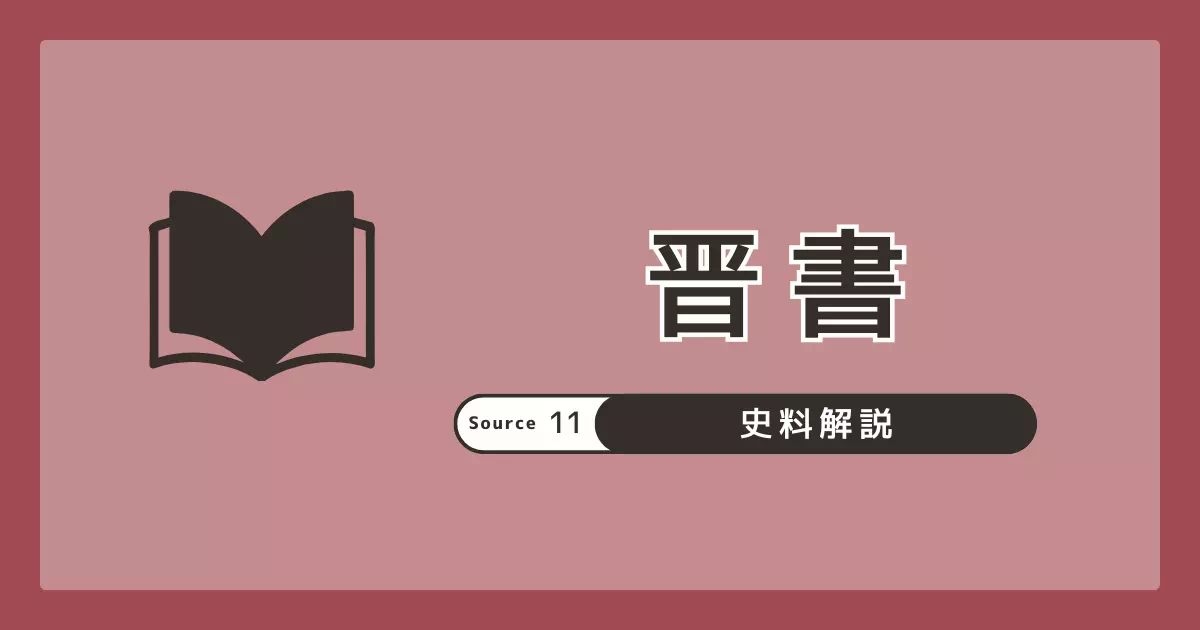
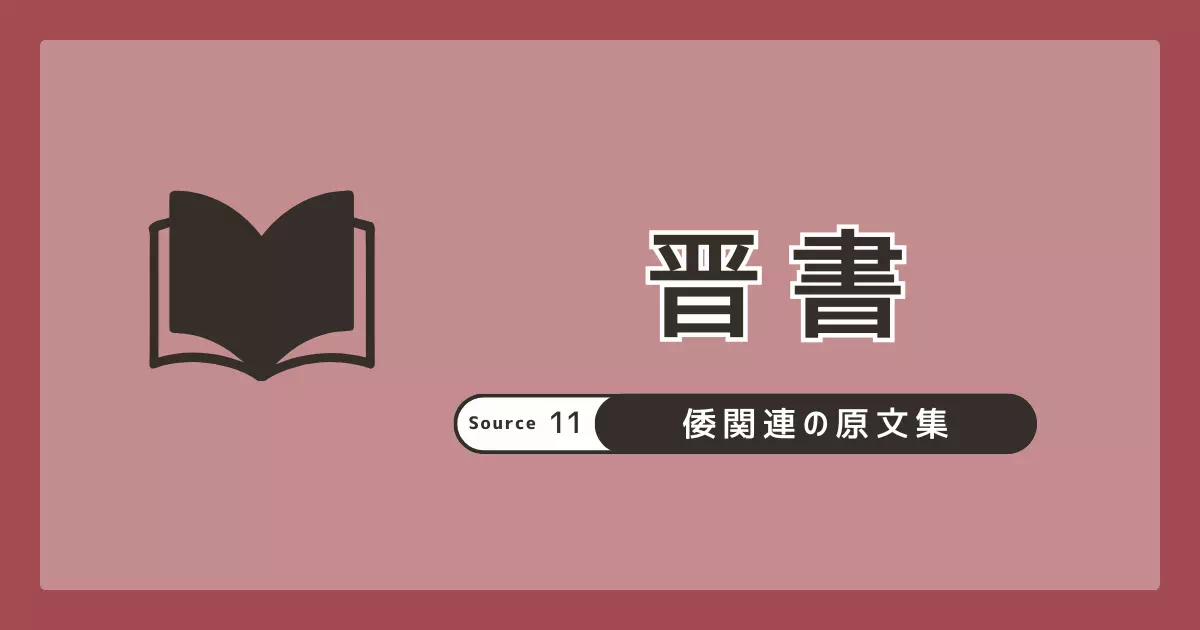
コメント