こちらの記事では、史料『翰苑』の倭や邪馬台国に言及した部分の原文のみを掲載しています。
解釈や補足説明を含まない構成となっており、原典の言葉に直接向き合うための資料としてご活用いただけます。
※文意の解説・現代語訳・学説比較については別記事にまとめております。
『翰苑』巻第30 蕃夷部
憑山負海鎮馬臺以建都
後漢書曰
倭在朝東南大海中 依山島居 凡百餘國 自武帝滅朝鮮 使譯通漢於者州餘國 稱王 其大倭王治邦臺 樂浪郡徼去其國万二千里 甚地大較在會稽東 与珠雀儋耳相近
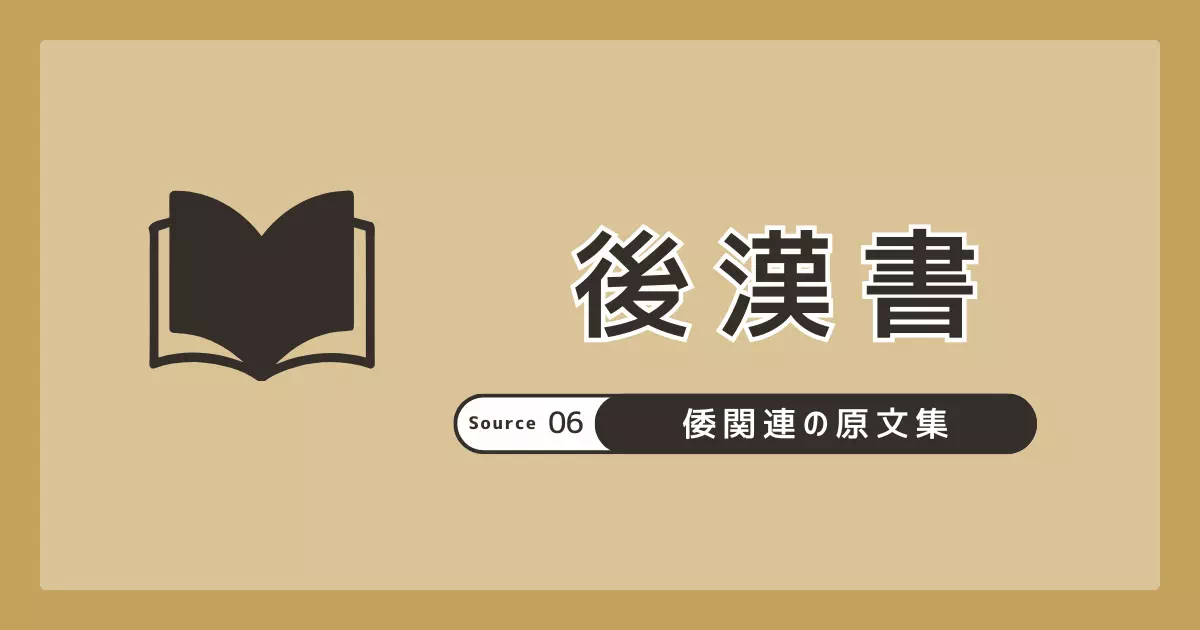
魏志曰
倭人在帶方東南 炙問倭地 絶在海中洲島之山 或絶或連 周旋可五千餘里 四面倶極海 自營州東南 經新羅 至其國也 倭人在帯方東南 参問倭地 絶在海中洲島之上或絶或連 周旋可五千余里 分軄命官統女王而列部
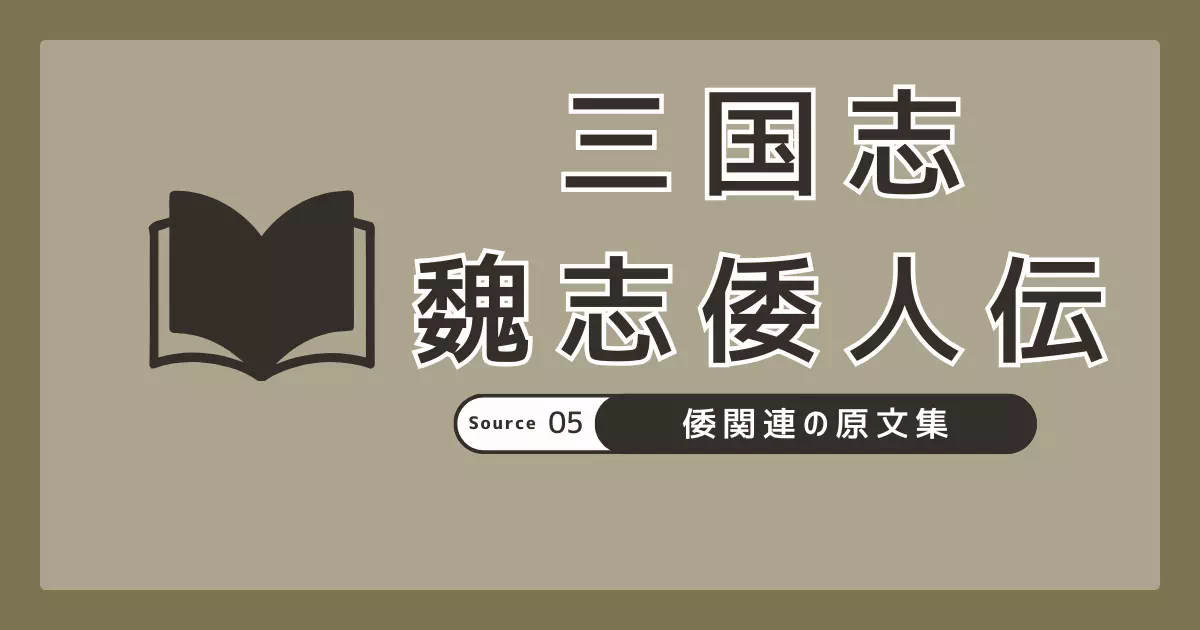
魏略曰
従帶方至倭 循海岸水行 暦韓國到拘耶韓国七十餘里 始度一海 千餘里至對馬國 其大官曰卑拘 副曰卑奴 無良田 南北布糴 南度海至一支國 置官至對同 地方三百里 又度海千餘里 至末盧國 人善捕魚 能浮没水取之 東南五東里 到伊都國 戸万餘 置曰爾支副曰洩溪觚柄渠觚 其國王皆屬王女也 卑彌娥惑翻叶群情臺與幼齒方諧衆望
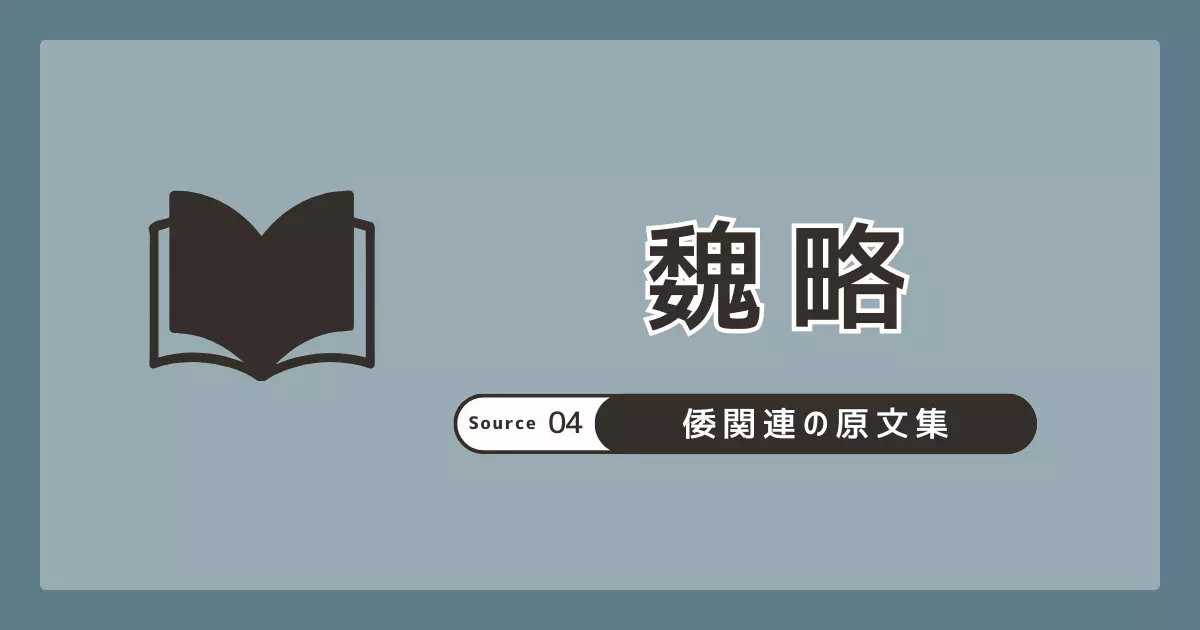
後漢書曰
安帝永初元年 有倭面上國王師升至 桓遷之間 倭國大乱 更相攻伐 歴年無主 有一女子名曰卑弥呼 死更立男王 國中不服 更相誅煞 復立卑弥呼宗女臺與 年十三為王 國中遂定 其國官有伊支馬 次曰弥馬升 次曰弥馬獲 次曰奴佳鞮之也
分身點面猶稱太伯之苗
魏略曰
女王之南 又有狗奴國 女男子爲王 其官曰拘右智卑狗 不屬女王也 自帶方至女國万二千餘里 其俗男子皆點而文聞其舊語 自謂太伯之後 昔夏后少康之子封於會稽 断髪文身 以避蛟龍之吾 今倭人亦文身 以厭水害也
阿輩雞彌自表天兒之稱
宋死弟 宋書曰
永初中 倭國有王 曰讃 至元嘉中 讃死弟珎立 自稱使持節都督安東大將軍倭國王 順帝時 遣使上表云 自昔祢 東征毛人五十五國 西服衆夷六 渡平海北九十五國 今案 其王姓阿毎 國号爲阿輩雞 華言天児也 父子相傳王 有官女六七百人 王長子号哥弥多弗利 華言太子
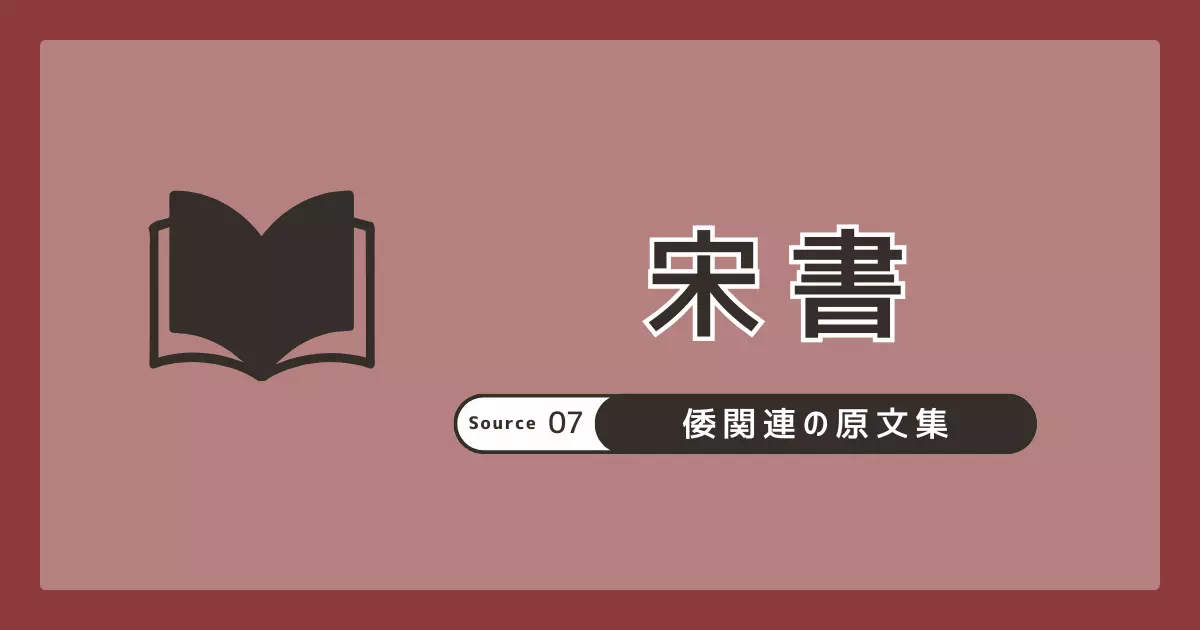
因禮義而標袟即智信以命官
括地志曰
倭國其官有十二等 一曰麻卑兜吉寐 華言大德 二曰小德 三曰大仁 四曰小仁 五曰六(大)義 六曰小義 七曰大礼 八曰小礼 九曰大智 十曰小智 十一曰大信 十二曰小信
邪届伊都傍連斯馬
廣志曰
倭國東南陸行五百里 到伊都國 南至邪馬嘉国 百女國以北 其戸數道里 可得略載 次斯馬國 次巴百支國 次伊邪國 安倭西南海行一日 有伊邪分國 無布帛 以革爲衣 盖伊耶國也
中元之際紫綬之榮
漢書地志曰
夫餘樂浪海中有倭人 分為百餘國 以歳時獻見
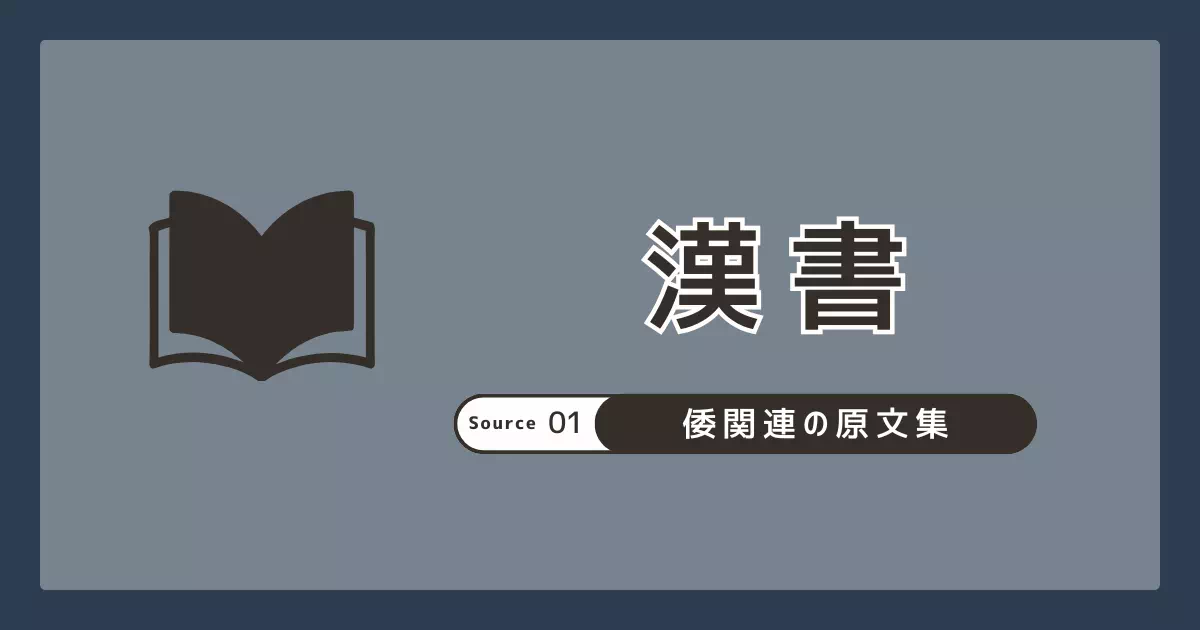
後漢書
光武中元年二 倭國奉貢朝賀使人自稱大夫 光武賜以印綬 安帝初元年 倭王師升等獻生口百六十
景初之辰恭文錦之獻
槐志曰
景初三年 倭女王遣大夫難升未利等 獻男生口四人 女生六人 斑布二疋二尺 詔以爲新魏倭王 假金印紫綬 正始四年 倭王復遣大夫伊聲耆振邪拘等八人 上獻生口也
翰苑とは?
翰苑の成立過程や信憑性などは、別途記事化しています。
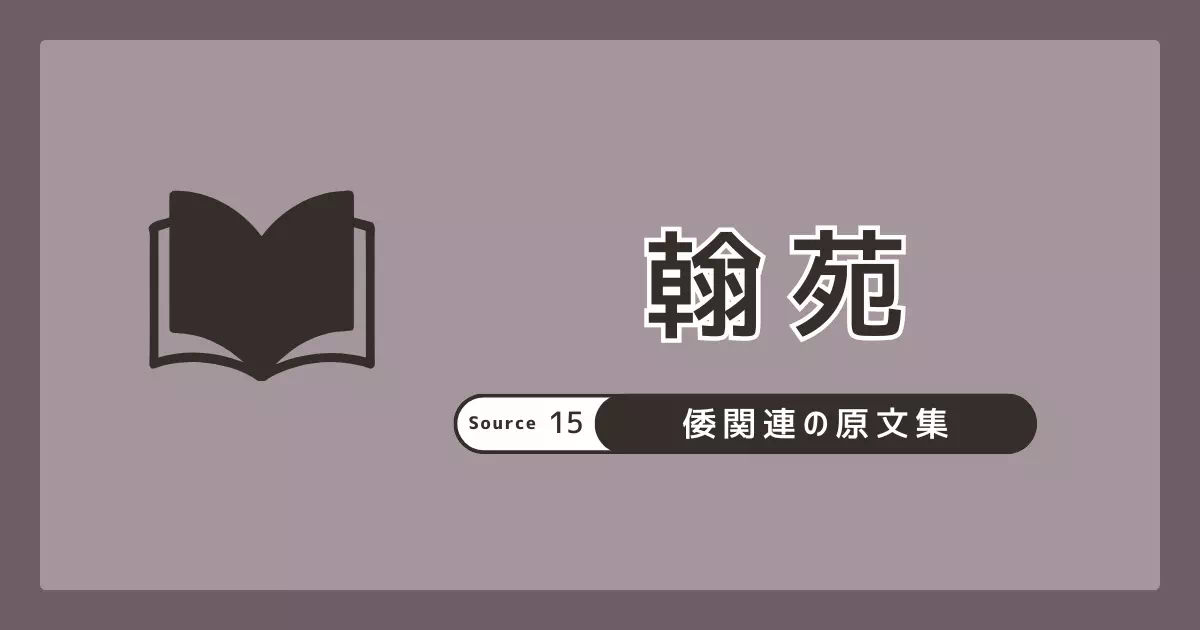
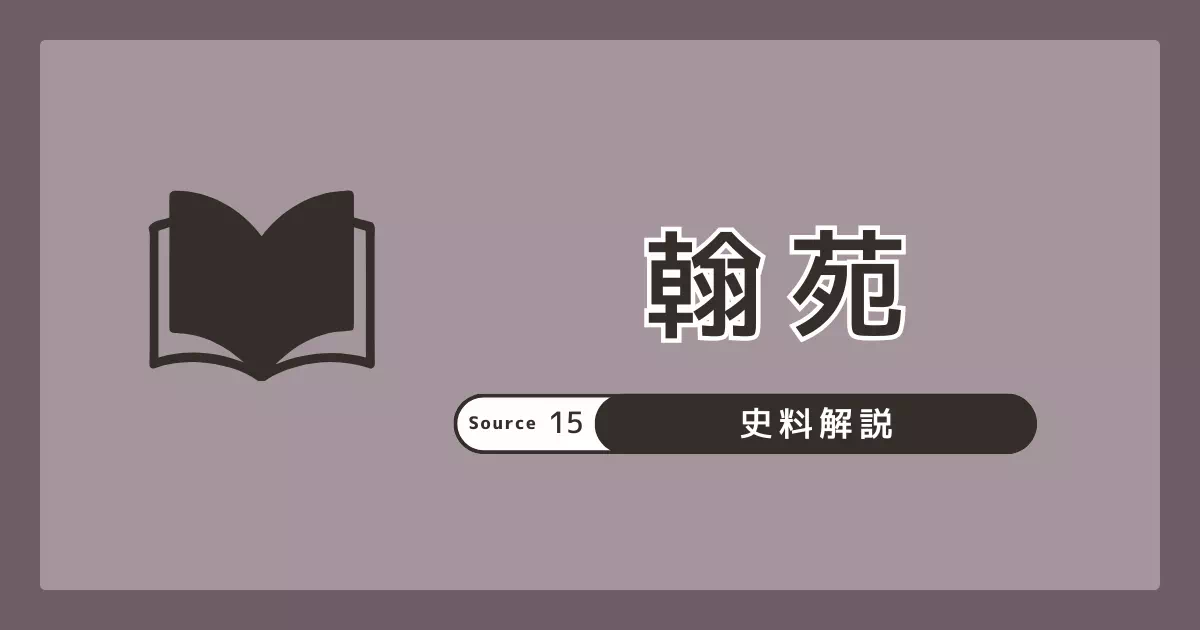

コメント