卑弥呼は中国の魏国に使者を送り、友好または主従(関係性は諸説あり)関係を築いたようです。
各史料に記載された功績
魏志倭人伝
景初二年六月、倭女王遣大夫難升米等詣郡、求詣天子朝献。太守劉夏、遣吏将送詣京都。
『三国志』魏書 巻30 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条
其年十二月、詔書報倭女王曰
「制詔親魏倭王卑彌呼:帯方太守劉夏遣使送汝大夫難升米(…以下略…)
景初二年に倭女王が魏に使者を出しています。
正始元年と正始四年にも「倭王」が使者を出して朝貢した記述がありますが、「女王」は登場しません。
正始八年には、再び倭女王が登場します。
正始元年と正始四年の使者は、前後の文の流れから倭王=女王が定説です。
一方で、女王とは意図的に区別した記述であり、卑弥呼以外の倭国の王が使者を出したとする説もあります。
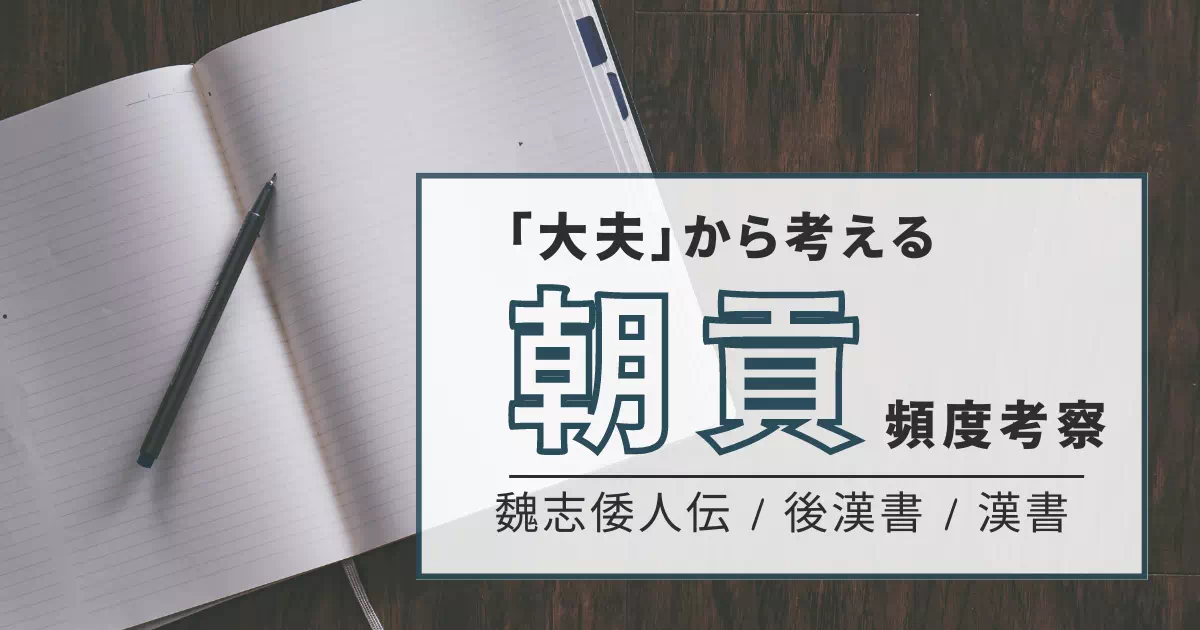
卑弥呼は狗奴国の男王・卑弥弓呼と前から不和だったようです。
其八年、太守王頎到官。倭女王卑彌呼與狗奴国男王卑彌弓呼素不和。
『三国志』魏書 巻30 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条
東夷伝と同じく三国志魏志の中の1書である三少帝紀にも、一文だけですが卑弥呼の記述があります。
影響が少ないこともあり、各論説では意図的に無視したり記述自体を知らずに触れないことも多い一文です。
冬十二月倭國女王俾彌呼遣使奉獻
『三国志』魏書 巻4 三少帝紀
先述の通り東夷伝にて、正始四年に倭王が使者を送ってきたという記述がありますが、女王とは明記されていませんでした。
一方の三少帝紀では、正始四年に「俾彌呼」が使者を送ってきたことになっています。
このことから以下2説が出ますが、一般的には「俾彌呼」は卑弥呼と同一とする考えが定説です。
- 俾彌呼 = 卑弥呼の同一人物説
-
正始四年に使者を送った倭王は女王を指す説。
- 俾彌呼と卑弥呼は別人説
-
実は「ひみこ」は巫女などの役職名であり、倭の各国に存在した。
正始四年に使者を送った倭王は女王とは別人であり、倭王の国の「ひみこ」と女王の国の「ひみこ」がそれぞれ使者を送ってきたとする説。
後漢書
桓靈間倭國大亂 更相攻伐歴年無主 有一女子名曰卑彌呼
『後漢書』巻85 東夷列伝 倭条
年長不嫁事鬼神道能以妖惑衆 於是共立為王 侍婢千人 少有見者
唯有男子一人給飲食傳辭語 居處宮室樓觀城柵皆持兵守衛 法俗厳峻
自女王國東度海千餘里至拘奴國 雖皆倭種而不屬女王
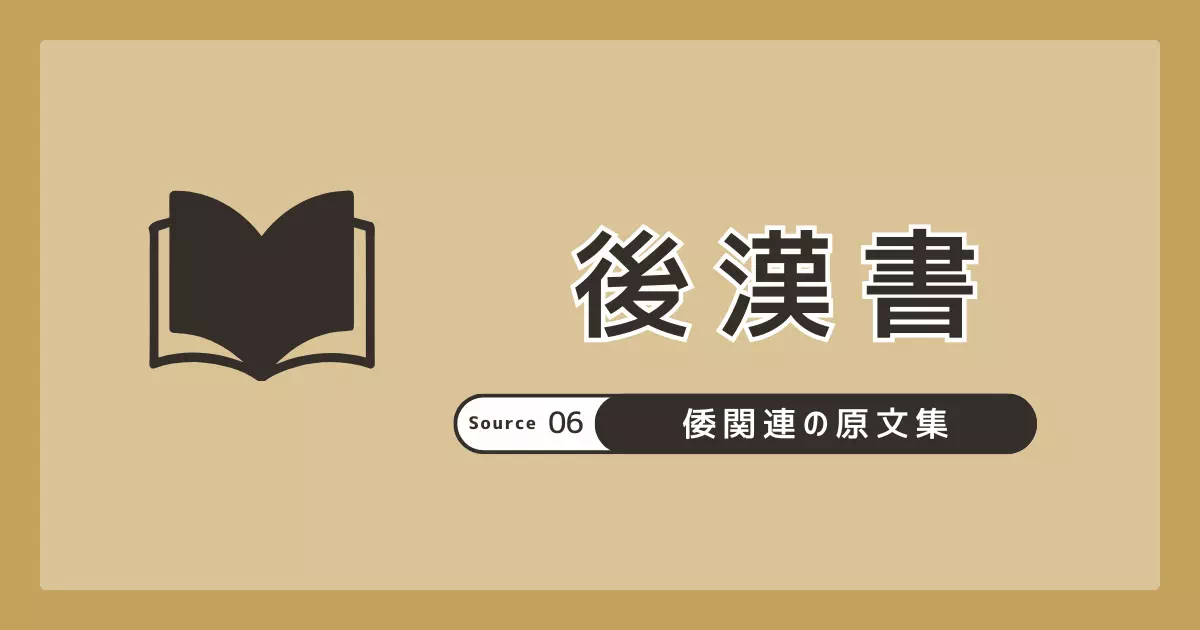
梁書
漢靈帝光和中,倭國亂,相攻伐歷年,乃共立一女子卑彌呼為王。彌呼無夫婿,挾鬼道,能惑眾,故國人立之。有男弟佐治國。自為王,少有見者,以婢千人自侍,唯使一男子出入傳教令。所處宮室,常有兵守衛。至魏景初三年,公孫淵誅後,卑彌呼始遣使朝貢,魏以為親魏王,假金印紫綬。正始中,卑彌呼死,更立男王,國中不服,更相誅殺,復立卑彌呼宗女臺與為王。
『梁書』巻54 列傳第48 諸夷 海南諸國 東夷 西北諸戎
隋書
漢光武時遣使入朝自稱大夫安帝時又遣使
『隋書』
朝貢謂之俀奴國桓靈之間其國大亂遞相攻伐歴年無
主有女子名卑彌呼能以鬼道惑衆於是國人共立爲王
有男弟佐卑彌理國其王有侍婢千人罕有見其面者唯有
男子二人給王飮食通傳言語其王有宮室櫻觀城柵皆
持兵守衞
三国史記
二十年、夏五月、倭女王卑彌乎遣使來聘。
『三国史記』新羅本紀 第2 阿達羅尼師今条
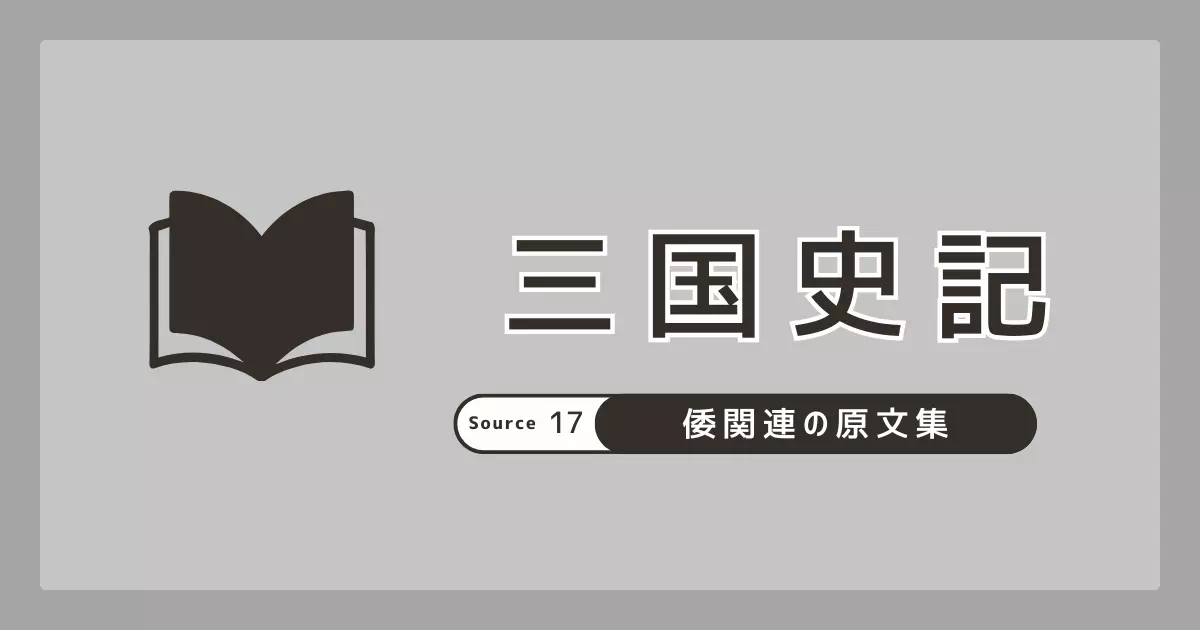
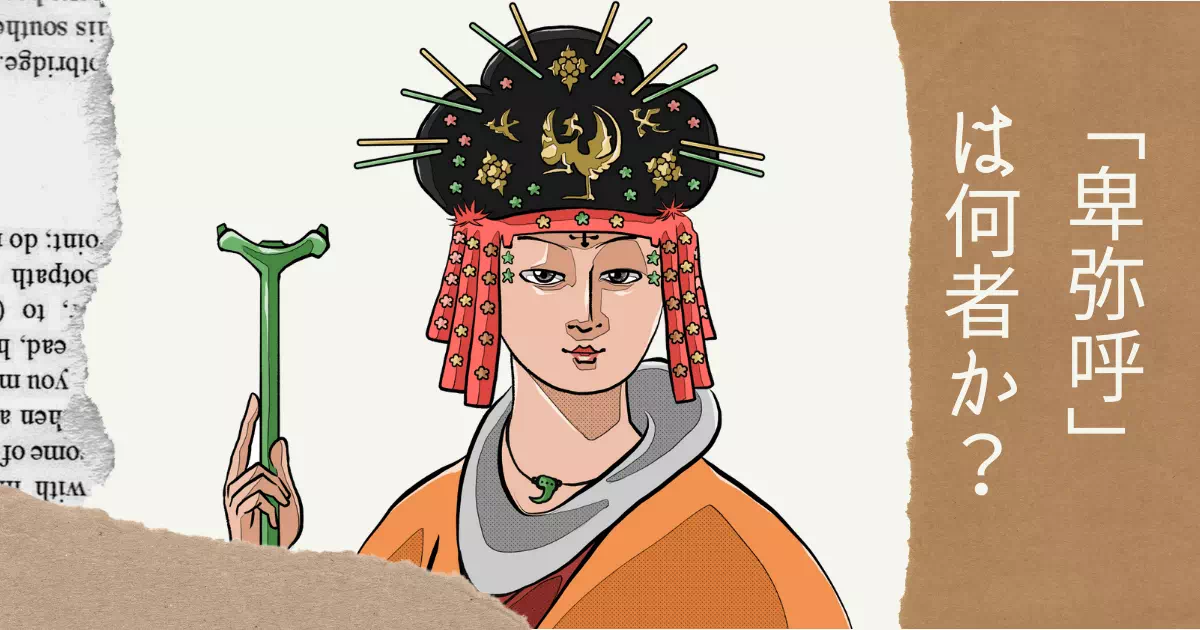
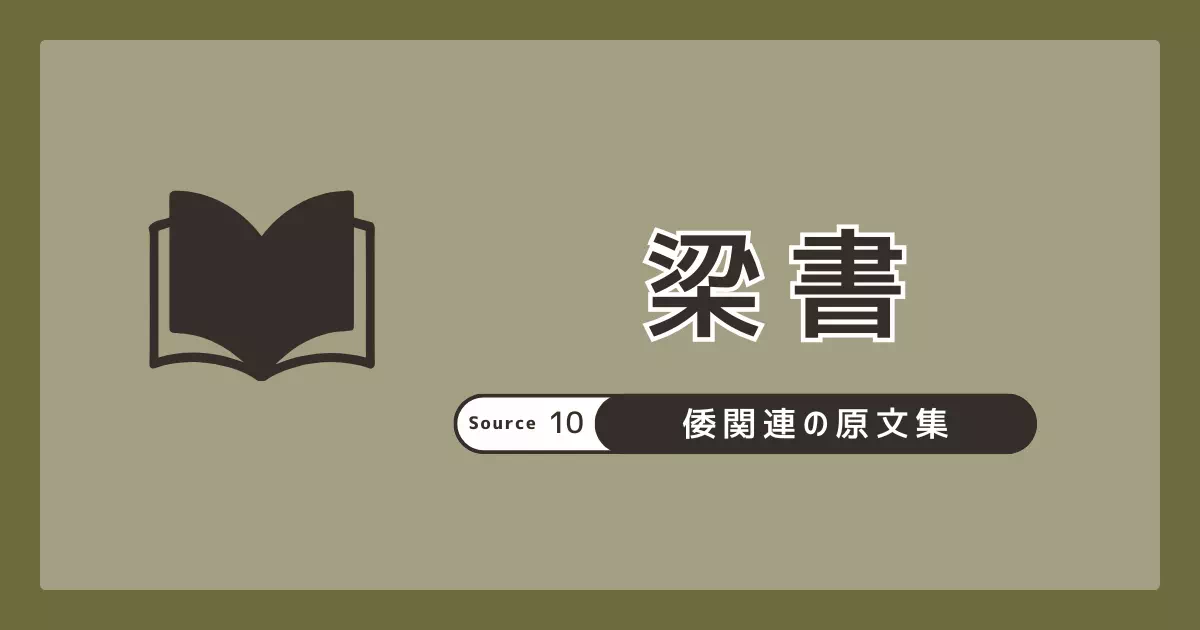
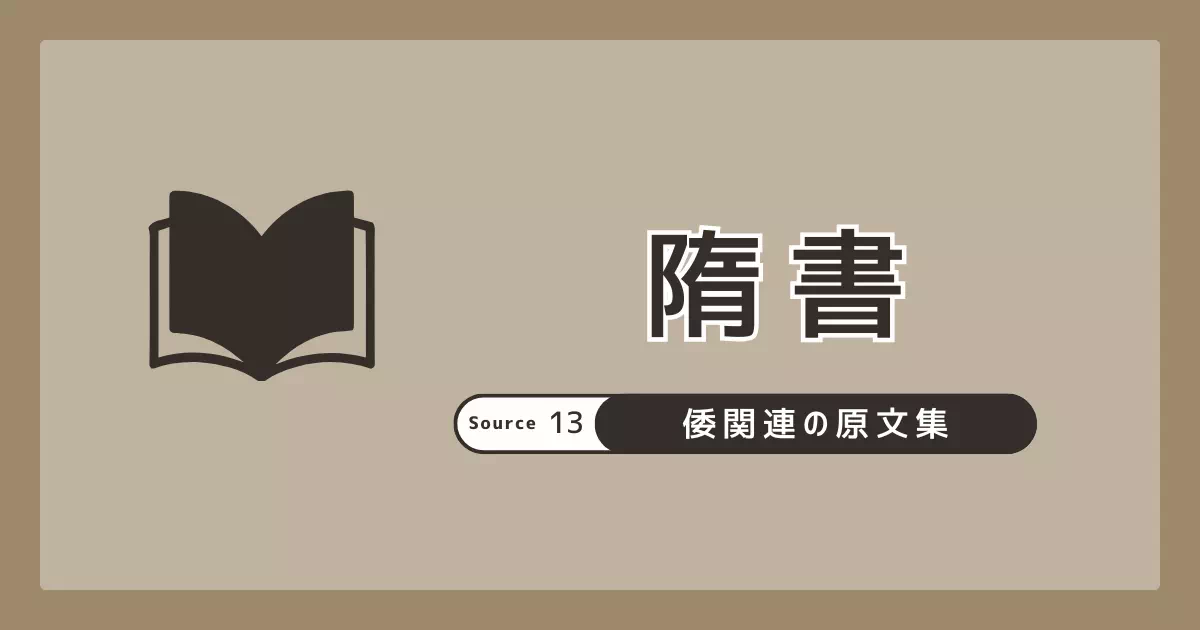
コメント