卑弥呼は邪馬台国研究における最重要人物ですが、その「読み方」には多くの謎が隠されています。
私たちは当然のように「ひみこ」と読んでいますが、史料には「卑彌呼」「卑彌乎」「俾彌呼」など複数の漢字表記が見られ、発音も「ひみこ」以外に「ひみほ」「ひみふ」など諸説存在します。
これらの違いは、当時の日本語や中国語の音韻体系、方言、そして漢字の使われ方を考慮しなければ解明できません。
本記事では、史料ごとの表記の違いを整理し、言語学・歴史学の視点から卑弥呼の本来の読み方に迫ります。
卑弥呼という名前の表記は複数ある

卑弥呼の名前は史料によって異なる漢字が用いられており、これが解読における混乱の一因となっています。
最も多く用いられるのが「卑彌呼」で、『三国志』魏書の「東夷伝」や『後漢書』、隋書、梁書などに記されている表記です。
一方で他の字形も存在し、同一人物を示す可能性が高い字体の揺れと考えられています。
しかし少数派ながら、別人物であるとする説も出ています。
| 卑弥呼の字 | 史料 |
|---|---|
| 卑彌呼 | 『三国志』魏書東夷伝 『後漢書』東夷傳 『隋書』東夷 倭國 『梁書』諸夷伝 |
| 卑彌乎 | 『三国史記』新羅本紀 |
| 俾彌呼 | 『三国志』魏書三少帝紀 |
厄介な点として、同じ『三国志』の中でも漢字が統一されていません。
漢字のバリエーションは、当時の書写技術や伝播経路、日本・中国双方の文献における異なる引用・翻刻と深く関係します。
『魏志倭人伝』とその後の歴史書が必ずしも統一した表記を使用していないことから、歴史家たちはそれらを総合しながら一つの人物として読み解いたと考えられます。
「卑彌呼」「卑彌乎」「俾彌呼」は、それぞれが同じ女王・卑弥呼を指す異なる表現とされ、現在では代表的な「卑彌呼」を中心に整理するのが一般的です。
漢字表記の違いは単なる文字の揺れにとどまらず、当時の文献の受け渡し過程や制度的な背景も加味しなければなりません。
これらを整理することで、読者にとって「卑彌呼」がどう記録され、どう理解されてきたのかが見えてきます。
「ひみこ」って正しいの?読み方の多様性
現在の私たちには「ひみこ」という読みが定着していますが、この読みが正しいとは限りません。
まず、中国語での当時の発音(中古音)では「卑(pie)彌(mie)呼(ho)」、上古音でも「呼(hag)」とされ、日本語側で「ほ」「ふ」に近い音だったと考えられています。
また、上代日本語の音韻構造では、「は行」音が「パ行」に近く変化しており、当時の「ho」「fu」が現代の「こ」とは異なる可能性も示唆されます。
さらに、「ひみお」「ひみを」と読む説もあり、漢字「呼」の本来の読みを重視すると、「を」音の可能性も指摘されています。
卑弥呼の読みは「ひみこ」「ひみほ」「ひみふ」「ひみを」など多様な候補が存在し、現代日本語による当て読みが後世に補完した可能性すらある!
このように、音韻学・漢字音の歴史的変遷・史料に基づく再検討を通じて、「卑弥呼」という名前が本来どのように呼ばれていたかを考えると、「ひみこ」一択ではないことが見えてきます。
読み方(音声付き)
「卑弥呼」
上古音:pieg-mier-hag
中古音:pie-mie-ho
魏書東夷伝の「卑弥呼」は現代中国語では以下のように発音されます。
音韻:Bēi mí hū
「俾彌呼」
魏書三少帝紀の「俾彌呼」を現代中国語で発音すると以下のように発音されます。
音韻:Bǐ mí hū
まとめ

卑弥呼という名前は、日本語では一般的に「ひみこ」と読まれています。
学校教育や歴史書、メディアでもこの読みが定着しているため、私たちはあまり疑問を持たずに「ひみこ」と呼んでいます。
しかし、史料における表記には「卑彌呼」「卑彌乎」「俾彌呼」などの揺れがあり、これらの違いは単なる写本の誤りにとどまらず、当時の発音や文化的背景の違いを反映している可能性があります。
また、読み方についても「ひみこ」だけでなく、「ひみほ」「ひみふ」「ひめこ」「ひみを」といった説が存在し、いずれも一定の言語学的根拠に基づいています。
特に、日本語の古音では「は行」が「ぱ行」に近い音を持っていたことや、中国語の古代音における「呼」の読みが「こ」とはかけ離れていたことを考慮すれば、「ひみこ」という読みが当時の実際の発音と一致していたかどうかは疑わしいと言えます。
さらに、倭人伝が書かれた当時の中国語、そして古代日本語や地域ごとの方言を踏まえた音の再構成には限界があり、卑弥呼が自らどう名乗っていたか、あるいは周囲がどう呼んでいたかを正確に突き止めることは非常に困難です。
結局のところ、「卑弥呼」の読み方には一つの正解があるわけではなく、複数の可能性を認識し、言語や文化、歴史の複雑な絡み合いを理解することこそが重要です。
現代の「ひみこ」はあくまで通用名であり、その背後には多様な音声的・歴史的背景があることを、私たちは意識しておくべきでしょう。
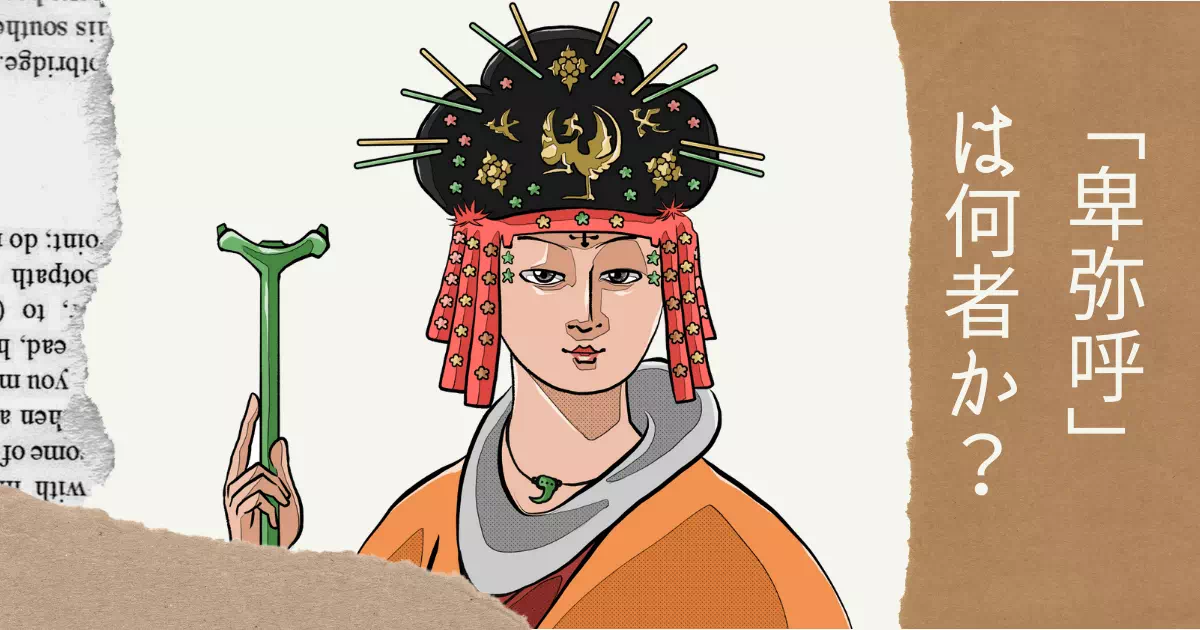
コメント