『翰苑』は魏志倭人伝をはじめ、倭に関して多くの書物を引用しつつ記述しています。
特に散佚した史料からの引用が重要で、邪馬台国と思われる記述もあり、貴重な史料です。
一方で、翰苑で引用された文と引用元の文を比較すると違いが多々あるため、全体的な信憑性は微妙です。
目次
翰苑とは
『翰苑』は張楚金が唐時代に著した中国の史料で、後年に雍公叡が注釈を付けています。
ほぼ散佚しているものの、日本の太宰府天満宮に第30巻(蕃夷部)と叙文の写本のみが残っており、国宝に指定されています。
翰苑巻第卅(かんえんかんだいさんじゅう)とも呼ばれています。

特徴として、原文は文字数が少なく、他の書物を引用した注釈が細かく記載されている点が挙げられます。
特にこの注釈が貴重で、同じく散佚している『魏略』を多く引用していることから、魏略の内容を知る貴重な史料にもなっています。
資料データ
| 著者 | 張楚金 |
| 成立年 | 660年(大唐顕慶5年、諸説あり) |
信憑性
メリット
- 現在は散佚した史料についても引用している
デメリット
- 引用元の文と異なる引用文も多い
他の史料を多数引用しているため、著者・張楚金の主観は少なめとされています。
『翰苑』は対句1練習用の幼学書2という説もあり、そのせいか誤字や脱字(脱文)と思われる記述も多くあります。
誤字脱字と判断できるのは、後漢書など現代まで残っている原文と比較することができるためです。
散佚した史料に関しては比較する術が無いため、散佚史料の引用部にも誤字脱字がある可能性があり、信憑性に欠けて真偽の判断や解釈が非常に難しくなっています。
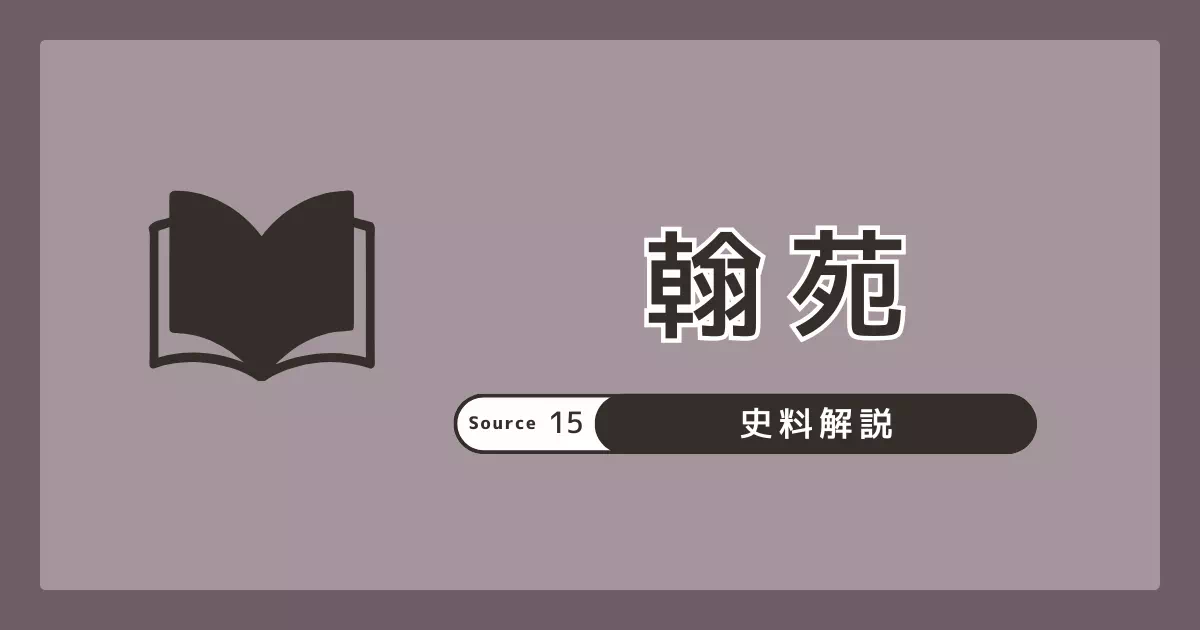
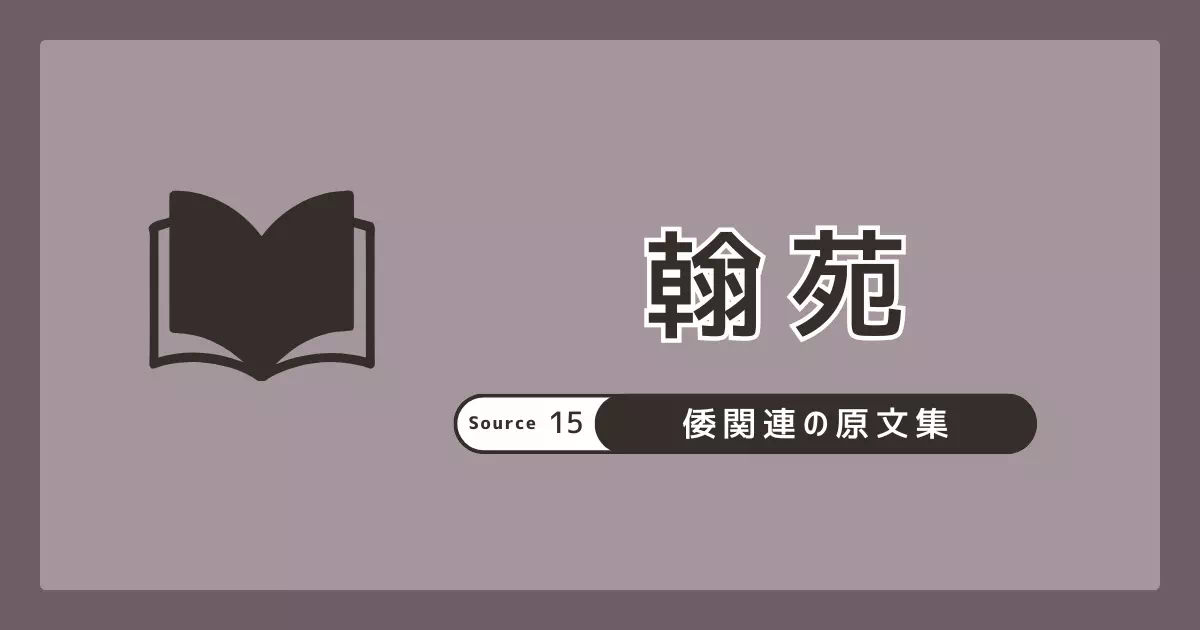
コメント