こちらの記事では、史料『梁書』の倭や邪馬台国に言及した部分の原文のみを掲載しています。
解釈や補足説明を含まない構成となっており、原典の言葉に直接向き合うための資料としてご活用いただけます。
※文意の解説・現代語訳・学説比較については別記事にまとめております。
『梁書』巻54 列傳第48 諸夷 海南諸國 東夷 西北諸戎
朝鮮半島
號所治城曰固麻 謂邑曰簷魯 如中國之言郡縣也
其國有二十二簷魯 皆以子弟宗族分據之
其人形長 衣服凈潔 其國近倭 頗有文身者
倭国
倭者自云太伯之後俗皆文身
去帶方萬二千餘里 大抵在會稽之東 相去絕遠
從帶方至倭 循海水行 歷韓國 乍東乍南 七千餘里始度一海
海闊千餘里 名瀚海 至一支國
又度一海千餘里 名未盧國
又東南陸行五百里 至伊都國
又東南行百里 至奴國
又東行百里 至不彌國
又南水行二十日 至投馬國
又南水行十日 陸行一月日 至祁馬臺國 即倭王所居
其官有伊支馬 次曰彌馬獲支 次曰奴往鞮
民種禾稻籥麻 蠶桑織績
有姜 桂 橘 椒 蘇 出黑雉 真珠 青玉
有獸如牛 名山鼠
又有大蛇吞此獸 蛇皮堅不可斫 其上有孔 乍開乍閉 時或有光 射之中 蛇則死矣
物產略與儋耳 朱崖同 地溫暖 風俗不淫 男女皆露紒
富貴者以錦繡雜采為帽 似中國胡公頭 食飲用籩豆
其死 有棺無槨 封土作塚 人性皆嗜酒
俗不知正歲 多壽考 多至八九十 或至百歲
其俗女多男少 貴者至四五妻 賤者猶兩三妻
婦人無淫妒 無盜竊 少諍訟 若犯法 輕者沒其妻子 重則滅其宗族
漢靈帝光和中 倭國亂 相攻伐歷年 乃共立一女子卑彌呼為王 彌呼無夫婿 挾鬼道 能惑眾 故國人立之 有男弟佐治國 自為王 少有見者 以婢千人自侍 唯使一男子出入傳教令 所處宮室 常有兵守衛 至魏景初三年 公孫淵誅後 卑彌呼始遣使朝貢 魏以為親魏王 假金印紫綬 正始中 卑彌呼死 更立男王 國中不服 更相誅殺 復立卑彌呼宗女臺與為王 其後復立男王 並受中國爵命 晉安帝時 有倭王贊 贊死 立弟彌 彌死 立子濟 濟死 立子興 興死 立弟武 齊建元中 除武持節 督倭 新羅 任那 伽羅 秦韓 慕韓六國諸軍事 鎮東大將軍 高祖即位 進武號征東將軍
其南有侏儒國 人長三四尺 又南黑齒國 裸國 去倭四千餘里 船行可一年至
又西南萬里有海人 身黑眼白 裸而醜 其肉美 行者或射而食之
文身國 在倭國東北七千餘里 人體有文如獸 其額上有三文 文直者貴 文小者賤 土俗歡樂 物豊而賤 行客不齎糧 有屋宇 無城郭 其王所居 飾以金銀珍麗 繞屋為緌 廣一丈 實以水銀 雨則流于水銀之上 市用珍寶 犯輕罪者則鞭杖 犯死罪則置猛獸食之 有枉則猛獸避而不食 經宿則赦之
大漢國 在文身國東五千餘里 無兵戈 不攻戰 風俗並與文身國同而言語異
梁書とは?
梁書の成立過程や信憑性などは、別途記事化しています。
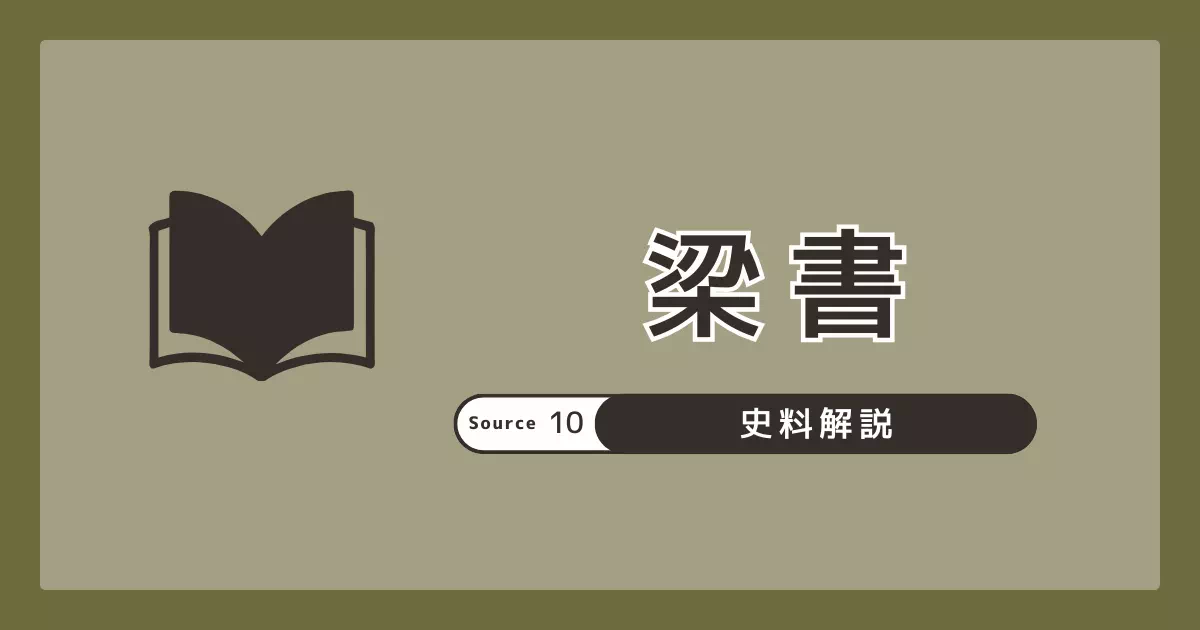
出典
原文を読む@中國哲學書電子化計劃
2025.01.14 閲覧確認
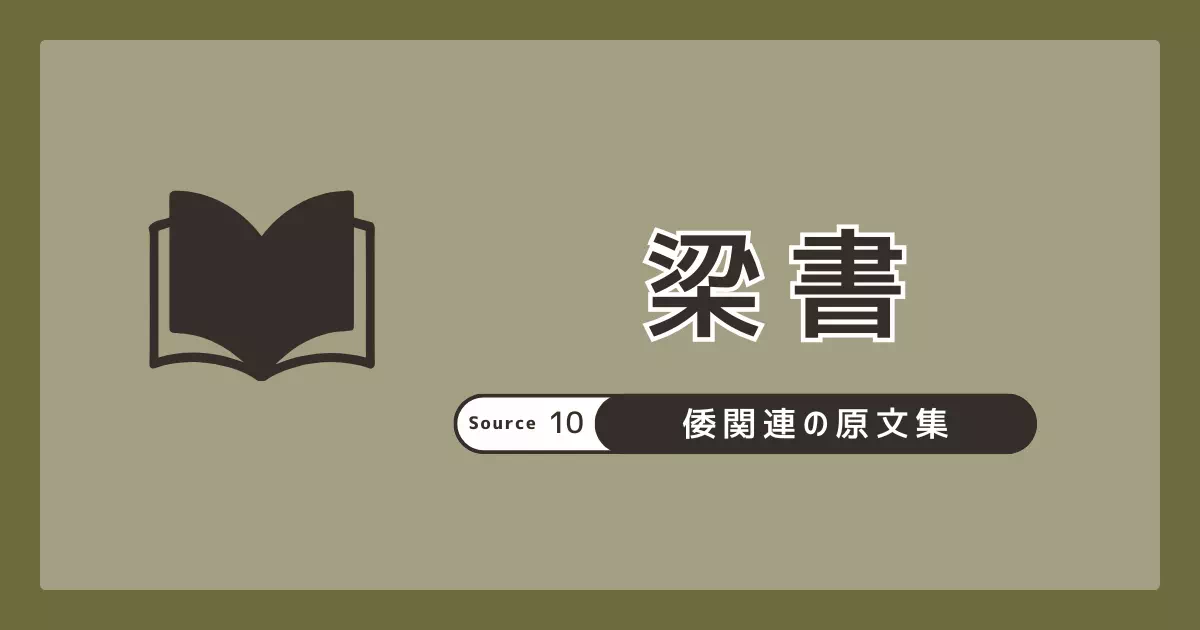
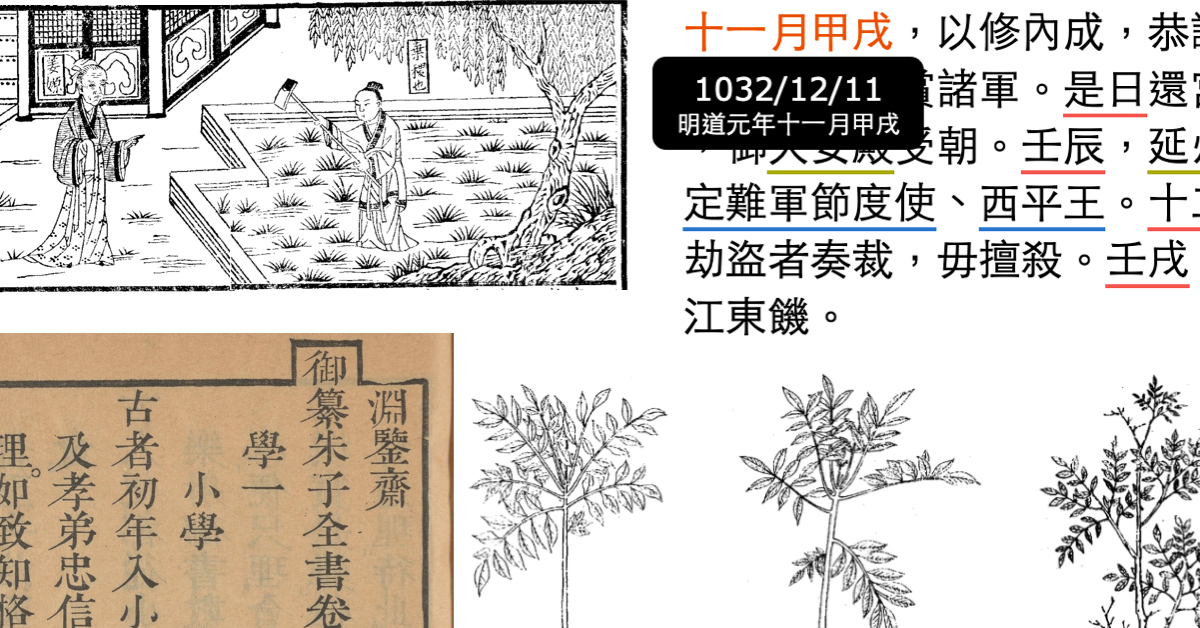

コメント